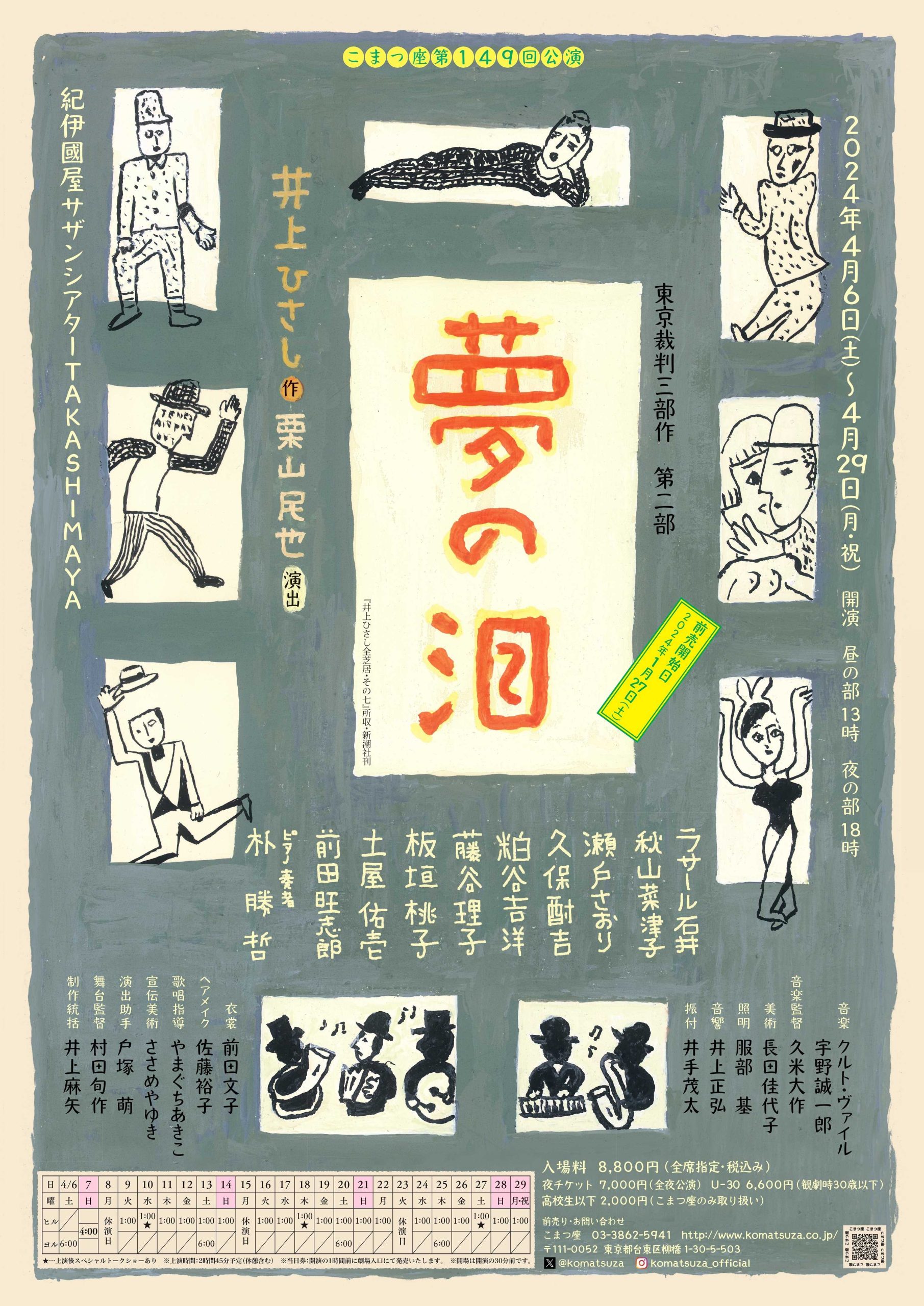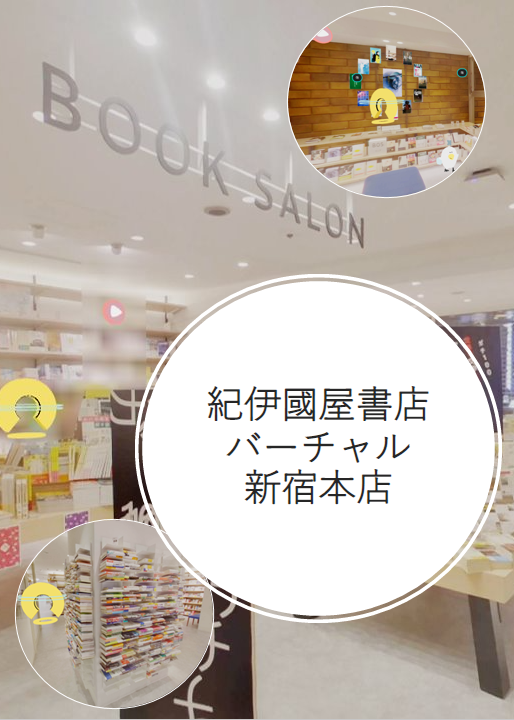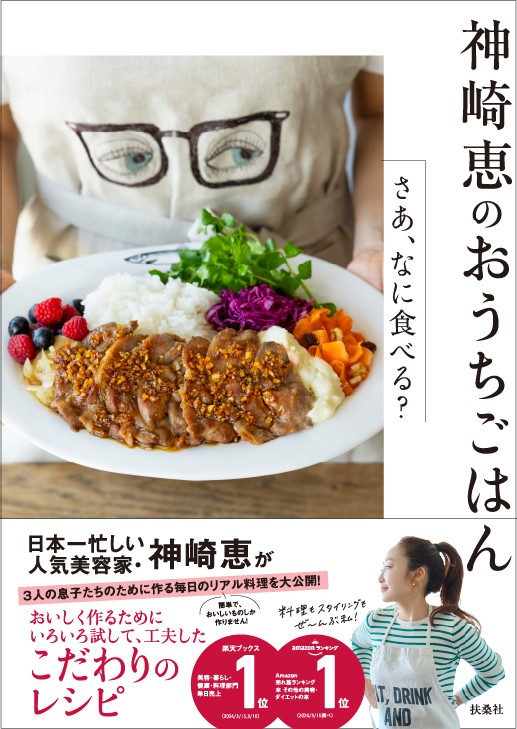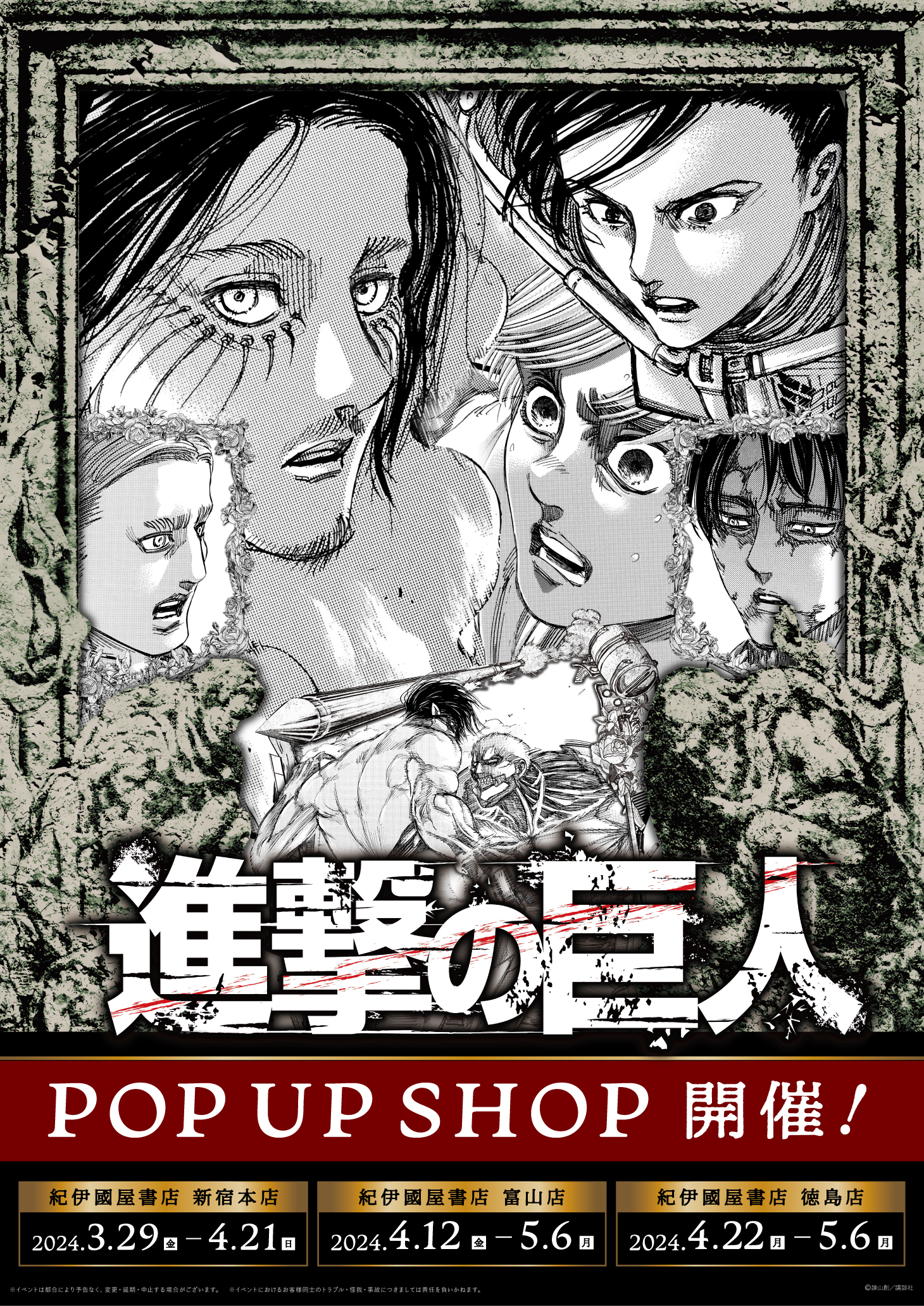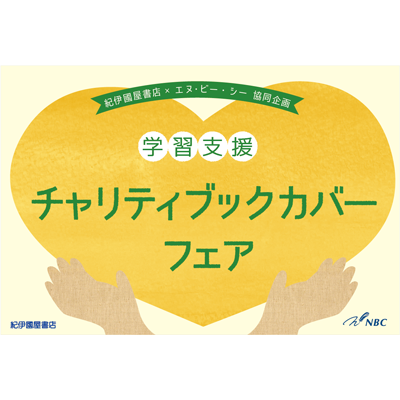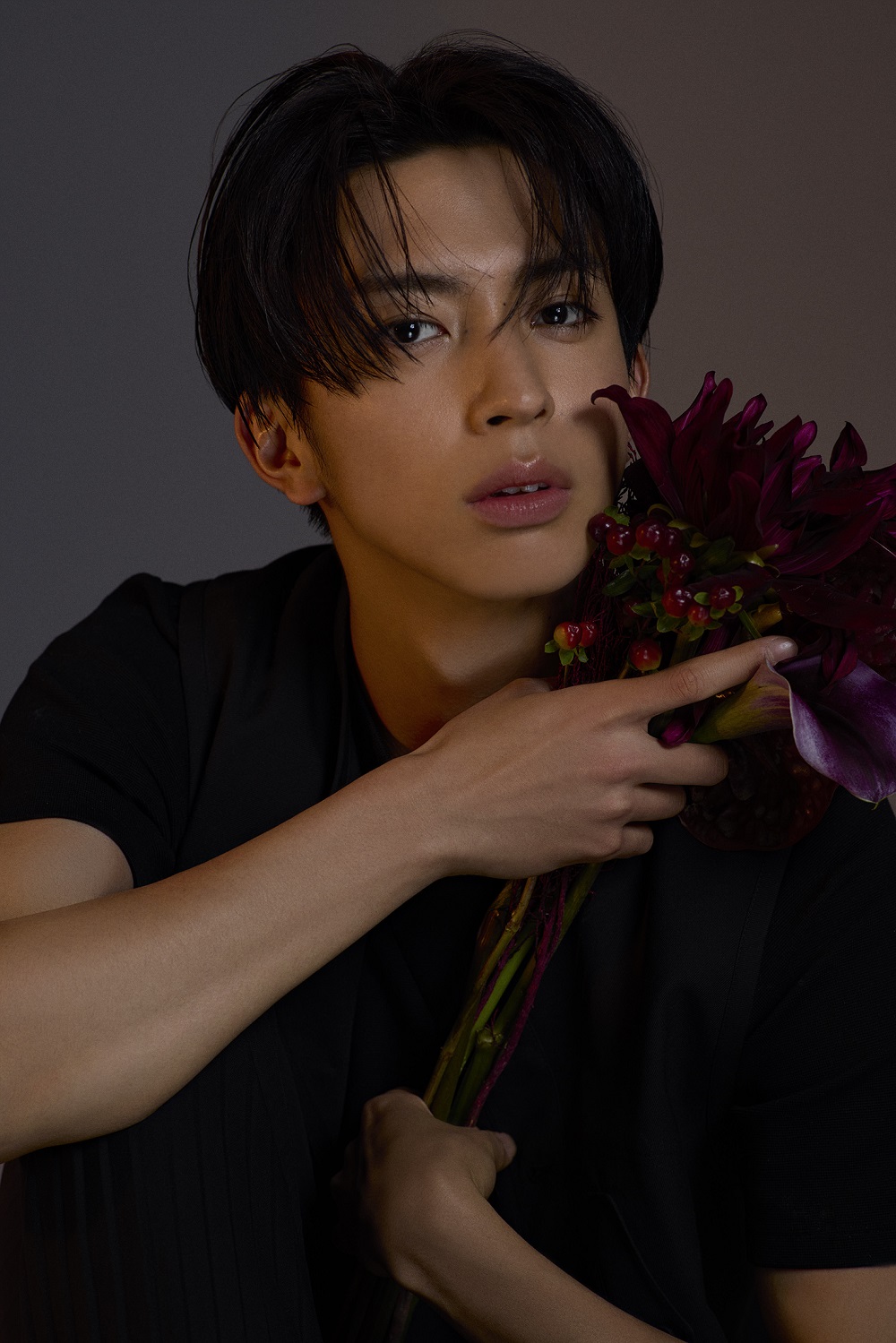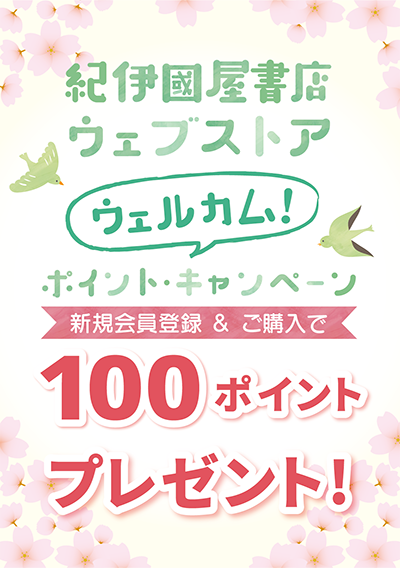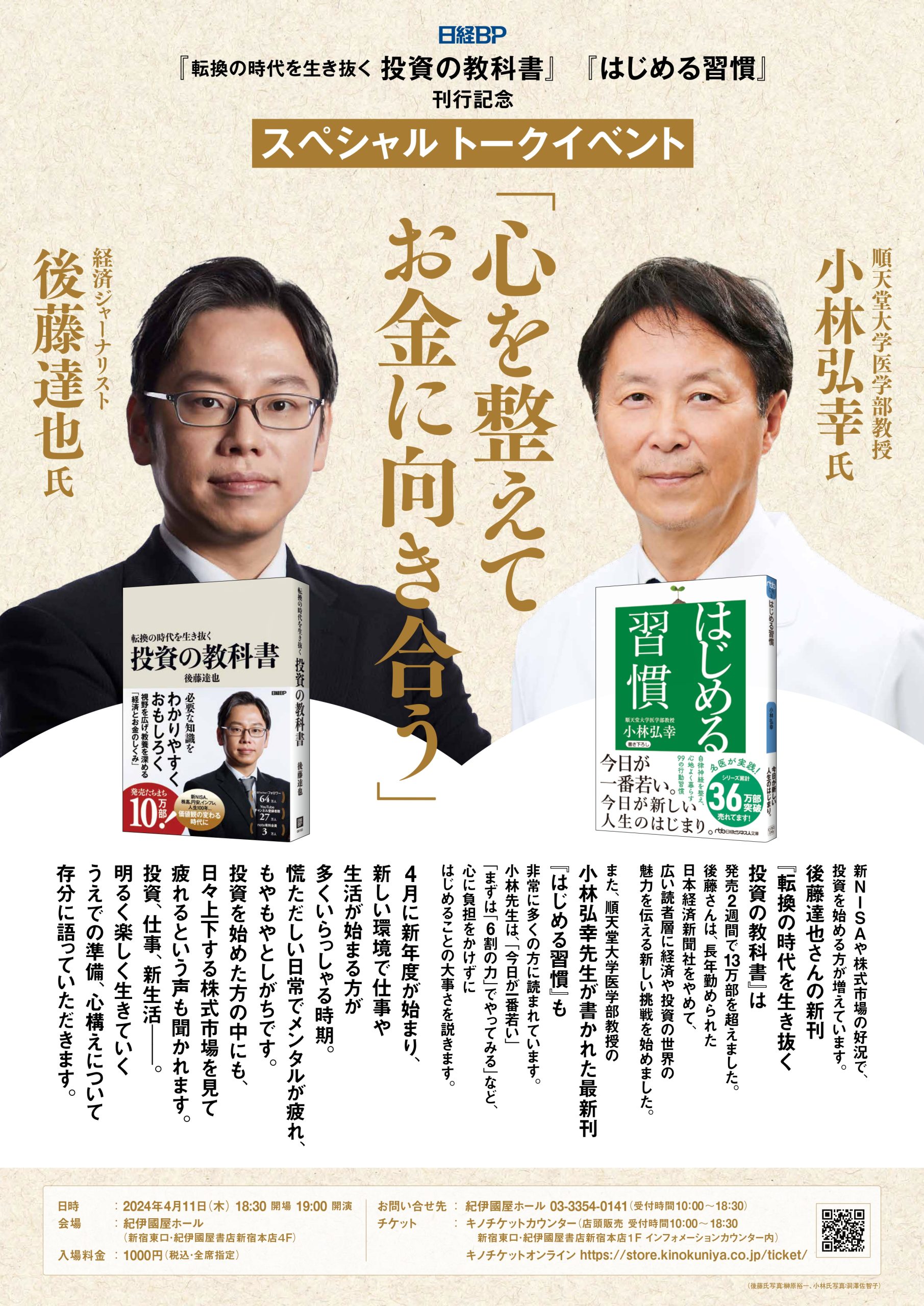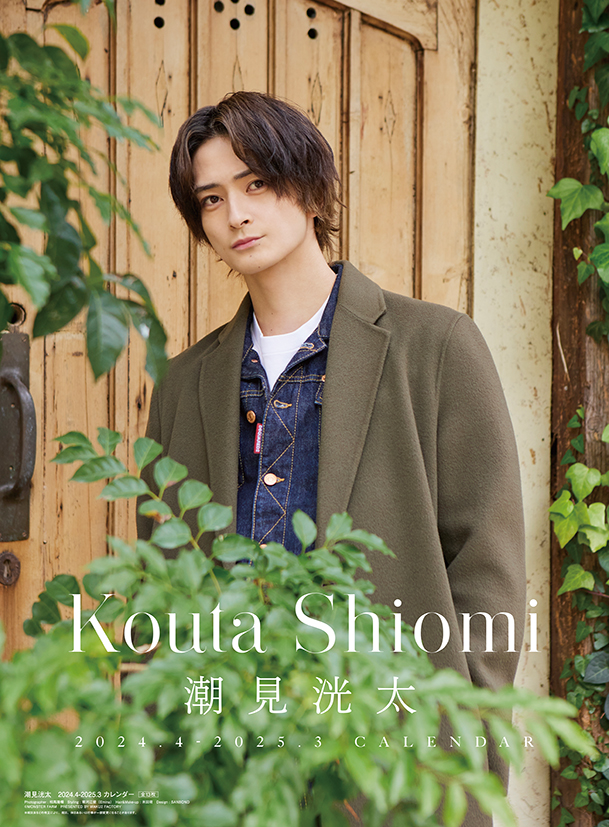この記事は https://corp.kinokuniya.co.jp/fukken2021/ をご覧ください。
書物復権によせて
宇野重規
(うの・しげき)1967 年生まれ。東京大学社会科学研究所教授・副所長。専門は政治思想史、政治哲学。『民主主義とは何か』(講談社現代新書)、『未来をはじめる』(東京大学出版会)など多数。階段上の狭くて広い空間
一昨年、在外研究で日本を留守にしているときに、我が家の改築問題が浮上した。妻が奮闘してくれたので、ほとんど任せきりだったのだが、設計図を見てふと思った。「僕の部屋はどこだろう?」。妻の答えは「ない」であった。二人の息子が大きくなったので、これを機にそれぞれに部屋を与えるという。
その方針自体はいいと思う。さらに妻は「いつも原稿は食卓で書いているじゃない」と追撃してくる。しかし、待ってほしい。筆者は一応研究者であり、人一倍本を抱えている。現在でもあふれている本をどうすればいいのか。これに対しても、妻はさらりと答えた。「この機会に整理すればいいじゃない」。
さすがにそれはないだろうということで、交渉の結果、二階への階段を上がったところに書斎を作ってもらうことにした。といっても、わずかな空間に本棚を設置したので、板机を除くとほとんどスペースがない。感覚的にはトイレ空間に等しいが、ドアもないので冬はまことに寒い。
にもかかわらず、この階段上の書斎、慣れてくるととても心が落ち着くことがわかってきた。置いてあるのは当然、厳選された、自分の好きな本ばかりである。そのような本のタイトルを見ているだけで、なんだか嬉しくなる。そういえば、政治思想家のハンナ・アーレントは、「自分を確認してくれるような物によって、世界が構成される」と言っている。その意味で、この書斎はまさに自分にとっての「世界」だ。
山のようにある文庫本もこの際に整理することにした。分類していると、いろいろ気づくことがある。例えば、これまで自分は大江健三郎の良い読者ではないと思っていたのだが、探してみると実にたくさんの本がある。やはり若い頃から、この作家の影響を受けてきたのだとしみじみ思った(調子に乗って、文芸誌に大江健三郎論まで書いてしまった)。
もちろん村上春樹の本も多いし、椎名誠の書くものが好きであることも再確認した。さらにいえば、橋本治についても、この才能ある著者の書くもののうち特定のジャンルに限られるとはいえ、かなりの本を持っている。いま自分が書いたり、話したりしていることは結構、この人の受け売りなのだと思った(再び調子に乗り、文芸誌に橋本治論を書いてしまった)。
ところで筆者の本業は政治学者である。文芸誌はともかく、政治学についての本はどこで書いているのかと聞かれるかもしれない。もちろん、この階段上の書斎である。いまどきの政治学者は大量のデータを駆使して論文を書くので、複数のパソコンやモニターを並べて、論文を書いている。筆者はこの狭い書斎で小さなノートパソコンと睨(にら)めっこしている。それでも、好きな本に囲まれたこの「世界」は、自分には広い空間だ。
コロナで家に閉じ込められていたこともあり、この書斎で『民主主義とは何か』(講談社現代新書)という本も書いた。この狭くて広い空間はますます居心地がいい。
⦿ご案内
毎年恒例の〈書物復権〉共同復刊、2021年は第25回を数えます。復刊の候補にあがったのは154点155冊と、充実したリストをそろえることができました。参加各社がそれぞれの出版の歴史のなかで、この後も読者に届けたいと考えている各分野の基本書です。
ぜひ、ご覧のうえリクエストいただき、1 点でも多くの復刊の実現にご協力ください。応募期間は2021年2月28日まで、ぜひ皆さまから多数のリクエストをいただけますようお願いします。
また今回も、通常では復刊が難しい少数の要望にも応えるべく、個別の注文に対応するオン・デマンド版での復刊も実施いたします。
※リクエスト投票受付は終了しました。
書物復権 参加出版社
●書籍の内容についてのお問い合わせは各出版社まで