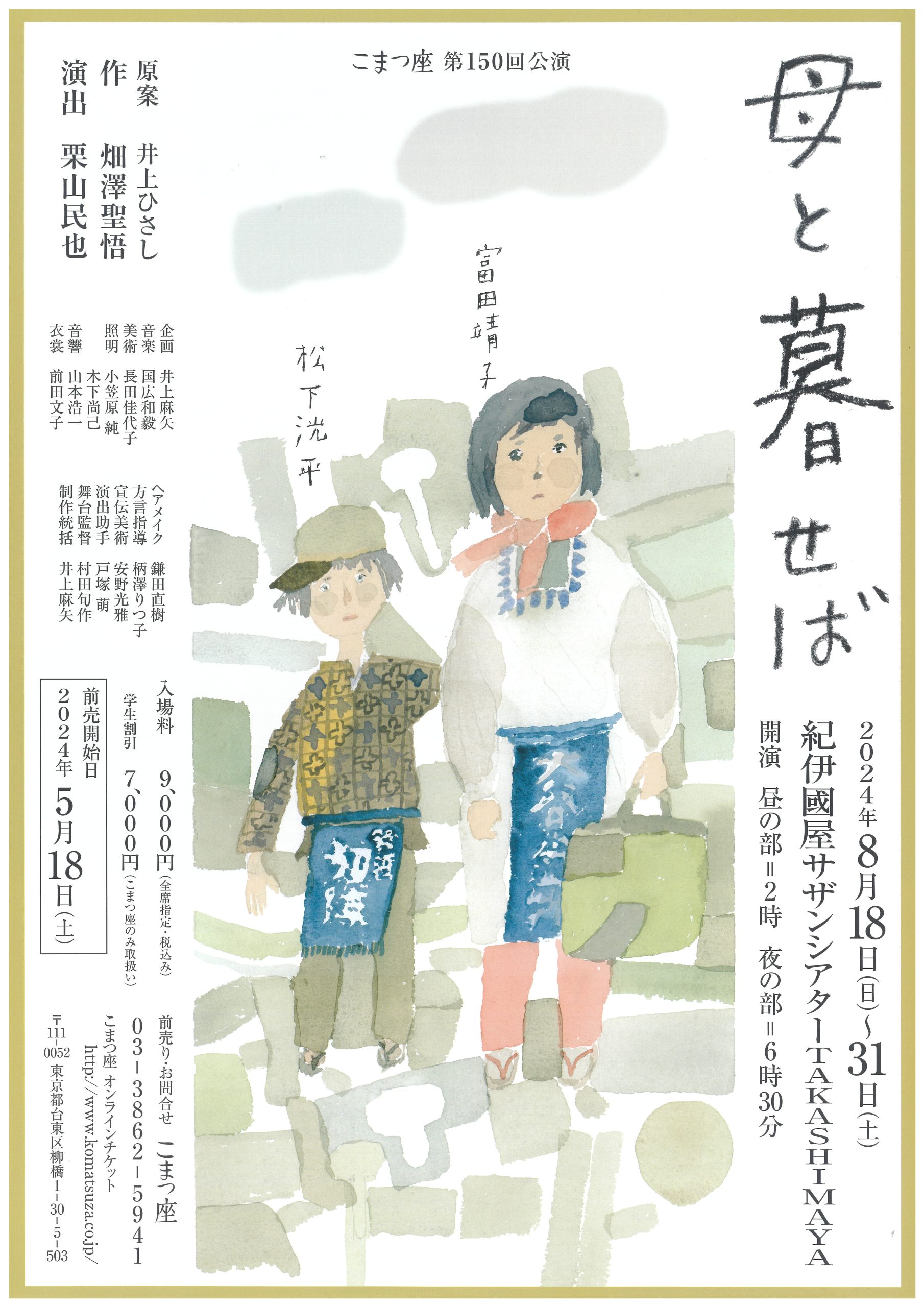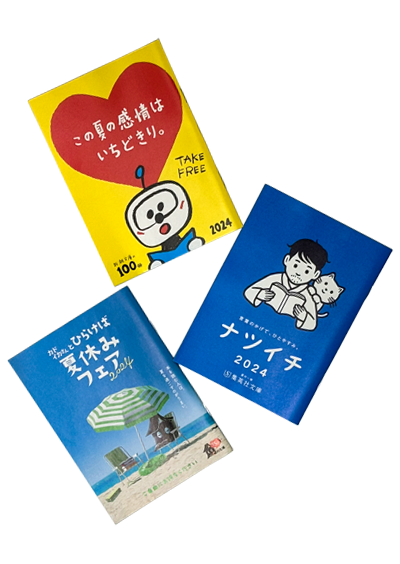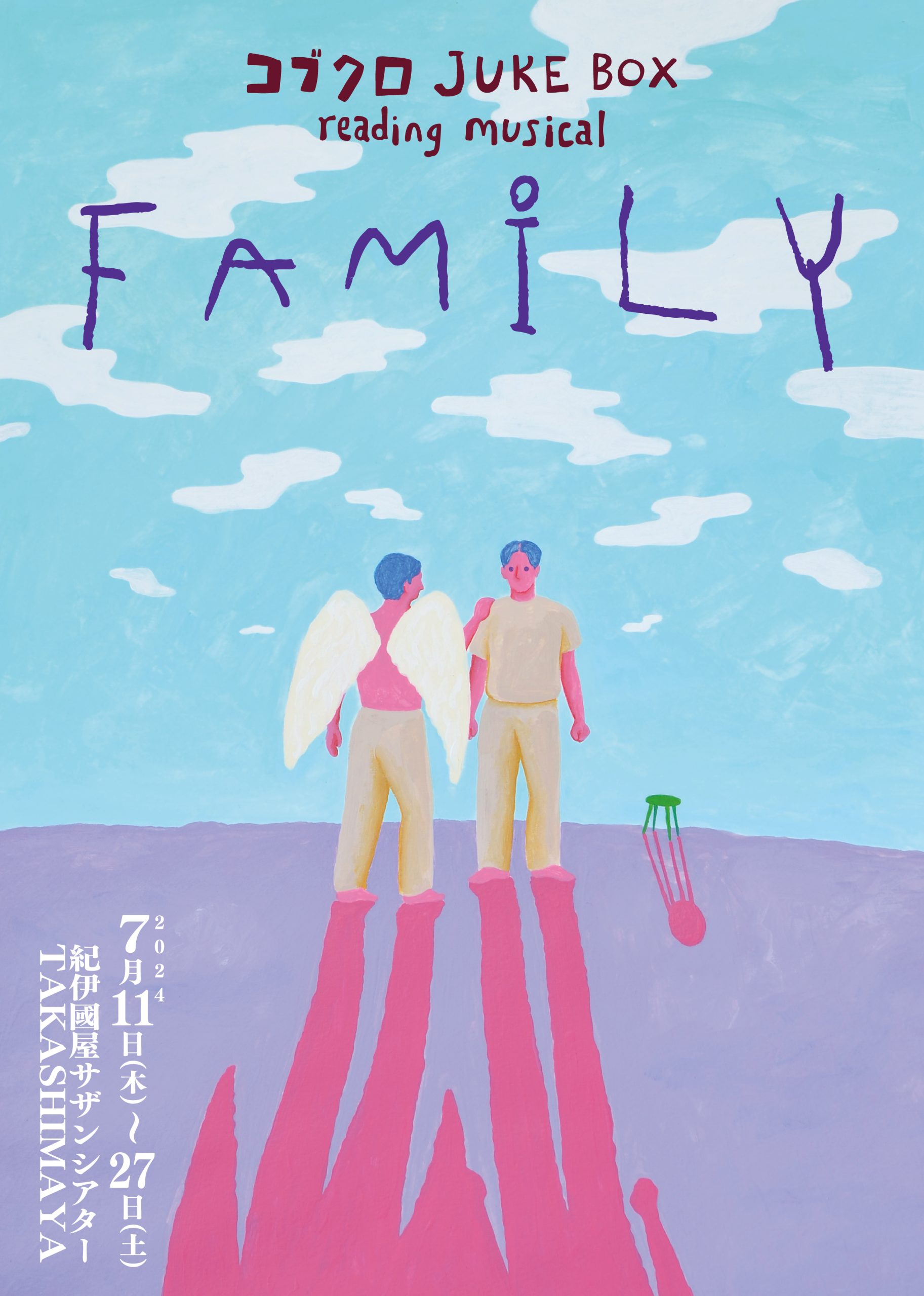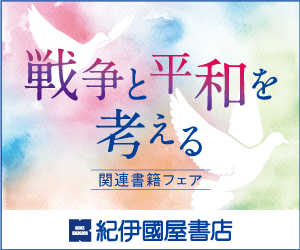
終戦後、広島・長崎をはじめ全国を駆け回り、悲しみの中にある人たちを励まし続け、敗戦国日本の再建策を提言した石原莞爾晩年の姿を、日記と多くの資料、証言をもとに描いたドキュメント。
戦後史の死角を衝く。「近代化」「大衆と市民」「ニューレフト」「新保守主義」をキーワードに解明する現代社会の特質。
戦後七十五年を迎え、戦争体験者の声が聞けなくなりつつある。しかしそもそも戦争の実相は聞く者へ伝わってきたのか?本書は語り手と聞き手との関係を問い直すことから始めて、「戦争のリアル」を捉えるための現代的方法を探る試みだ。膨大なテレビドキュメンタリー、若い世代の受け止め方の変遷、そして語りによる伝承を綿密に分析することによって「語る‐聞く」パターンの限界を浮かび上がらせたうえで、視聴覚メディアを題材に継承の場を作る条件を明らかにする。「アーカイブ」の創造的活用を実証する、類例のない提言の書。
あの日々をどう生きたか。手記、手紙、絵、写真―157の体験。これが戦争なのだ。
戦争孤児の実態を数値や制度上で把握するだけではなく、一人の生の記録として着目。孤児になる経緯・ジェンダーなどの視角を重視し、現代的観点から孤児問題を考える姿勢を提示する。聴き取り調査の手法や年表も掲載。
ワシントン州シアトルで、広島県出身の父・克二と母・キヌのあいだに4男1女の次男として生まれたハリーは、父・克二の死後、母キヌと兄弟・姉とともに広島に移住するが、日本に馴染めず、1938年に帰米。ところが、1941年アジア太平洋戦争勃発に伴い、一年後にハリーの後を追って帰米した姉のメアリーとともに、アリゾナ州のヒラ・リバー強制収容所に収監される。一方、ハリーの兄ヴィクターと弟のピアス、フランクは母とともに広島に残った。太平洋戦争前に召集を受けたヴィクターだけでなく、やがて彼ら三人ともが帝国陸軍に召集される運命にあった。日米開戦によって二つの祖国のあいだで身を引き裂かれた日系人の生を描く壮大な歴史絵巻。
1942年収容所にいたハリーは、アメリカ陸軍情報部語学兵試験に合格し、翌43年夏には、第33歩兵師団付の語学兵として、ニューギニア戦線やフィリピン戦線に赴き、日本兵と対峙。赴任当初は、陸軍内で差別を受けるが、戦況が進むにつれ、日本軍から鹵獲した機密書類の翻訳や日本人捕虜の尋問の成功などの実績により、陸軍内での信頼を勝ちえていく。やがて、九州上陸作戦への従軍を聞かされていたハリーに、広島への原爆投下の一報が入る。日系二世が直面した強制収容、人種差別やアイデンティティ・シフト、米国に従軍した日系人の戦争協力、原爆投下によって壊滅的被害を受けた広島―。戦争に人生を翻弄された日米双方の市井の人々の経験を、あざやかな筆致で描き出す叙事詩。
あの戦争で、日本は何を失ったのか?最盛期には800万人を超える兵力を動員し、途方もない額の戦費を使い、国力を限界まで傾け、持てる人的資源、物的資源を注ぎ込む―。太平洋戦争は日本にとって、文字通りの“総力戦”になった。昭和16年12月8日の真珠湾攻撃、マレー上陸作戦から、昭和20年9月2日の戦艦ミズーリ甲板上での降伏文章調印まで、3年9ヵ月にわたってつづいたこの戦争で、日本は多くの人命を失っただけでなく、多くの財産が無に帰され、官民の在外資産、海外領土を喪失した。はたしてその損失はどれほどのものだったのか。また、戦後に国際社会に復帰するためにどれほどの賠償をおこなったのか。太平洋戦争を戦費・損失・賠償など、金銭面から解剖。かつてない戦争の姿が見えてくる。
キヨシの住んでいた東京の下町は、東京大空襲で焼け野原となった。戦争はむなしく終わり、福島のおばあちゃんのもとに疎開していたキヨシは、東京へ家族をさがしにいく。食べるものもままならない戦後直後、おばあちゃんがもたせてくれたのは、五つのおにぎり。大切なおにぎりをリュックサックに入れ、焼けあとをさまようキヨシが見つけたものとは?











.jpg)